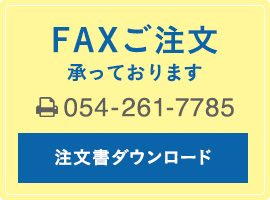Hゴム
観音扉には門口(門枠)との接触面に雨水の侵入を防ぐためのパッキンである、Hゴムが使用されています。Hゴムは、塩ビの素材で硬さや扉の厚みにより様々な種類があります。
荷物の品質を保つにはHゴムの管理が必要不可欠
トラックの観音扉には防水性を高めるために、扉との境界部分にHゴムが使用されています。Hゴムは長期間紫外線や雨水、雪に晒されると、経年劣化と共に素材自体の弾力が無くなっていきます。またHゴムの劣化は、観音扉の芯材であるベニヤやMDF材まで水が侵入して、表面材のアルミが浮いたり剥離したりする原因にもなります。そのため、本来の目的を果たせなくなる前に、Hゴム自体を交換しなければいけません。
雨水の荷台内への侵入は、積荷の品質にも影響しますので、Hゴムの状態を確認し、早めに交換することをおすすめします。
Hゴムの種類
Hゴムには「接着型」と「軟質型」があります。
「接着型」はツーピースガスケットとも呼ばれるHゴムです。ツーピースとは、門口(門枠)の接触面は軟質型と同等の柔軟性がありますが、扉への設置面は固く変形量が少ない素材でできております。このため、Hゴムと扉との密着性が良く防水性を高めやすい構造です。観音扉の芯材に対しては、Hゴムをシリコンコーキングで接着します。設置後の扉とHゴムの縁には、コーキング処理して防水性を高めます。
「軟質型」は、30年以上前の観音扉に主に使用されてきた素材全体が軟らかいHゴムです。当時は、Hゴムをリテーナーと呼ばれるアルミの薄い板で挟み、観音扉の芯材に対してホチキス状のもので打ち付けて設置しておりました。この方法ですと、観音扉の芯材に対する防水性が低く、長く使用すると水が浸入して扉が膨らんだり腐ってしまいやすいという欠点がありました。素材自体が軟らかいため、防水性は劣りますが、多少の扉の厚みには対応できます。
「接着型」のサイズは「13mm」「16mm」「19mm」と、扉の厚みに応じたものがあります。「19mm」のサイズは、長さが「2500mm」と「3000mm(低床トラック用)」をお選びいただけます。取り付ける扉の厚みや大きさに適したものを選びましょう。
ヤマダボディーワークスでは、Hゴムの他にも観音扉を製作する為の必須部品である防水テープやコーナータブ、コーナーロック、塩ビ専用接着材なども取り扱っております。また、跳ね上げ扉を製作する際に必要な、テールゲートのプラットフォームとの合わせ目に使用するアルミ材、防水パッキンゴムなど専用部品も取り扱っております。